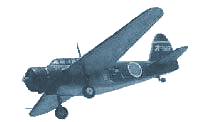
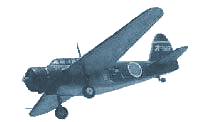
|
海軍第一期飛行専修予備生徒 |
|
|


|
||
 |
 |
|
|
海軍少尉候補生(左) 海軍少尉飛行服(右)に身を包む |
||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
九七式艦上攻撃機(中島 B5N2) 1937年当時としては最新の技術である単葉、可変ピッチ、フラップを装備した艦上攻撃機だった。
|
||||||||||||||||||||||
|
下記文中の数字は「海軍飛行科予備学生・生徒史」より転載しました。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
海軍飛行専修予備学生 |
帝國海軍創設以来、有事の際に海軍将校を補う為に予備将校の養成制度を設け、予備将校は明治37年6月以降の官階に定められ、兵科将校の予備員とするものであった。 満州事変の勃発後、国際情勢の急変に伴い戦時要員の充足と航空戦力の増強が必要となり、昭和8年12月に航空予備員に関する方針が決定された。これが帝國海軍における予備学生制度の嚆矢をなすものである。 海軍における航空戦力の重要性が認識され始めた昭和9年、飛行機搭乗士官の不足に備え、海軍が旧制大学・高等専門学校の卒業生から志願制によって採用したのが飛行予備士官制度である。 当初は数も少なく1期学生は僅かに6名だったが、年を追って増加し大東亜戦争の勃発と共に昭和17年には9~12期・328名が戦列に加わり、航空決戦が熾烈となった昭和18年には一挙に5,200名が13期として馳せ参じた。 同年12月には「学徒出陣」によって現役入隊した大学・高専在学生のうち3,334名が14期学生として加わった。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
太平洋戦争開戦 |
昭和16年12月 ハワイ真珠湾攻撃 | |||||||||||||||||||||||||
|
海軍飛行専修予備生徒 |
大学・高専を卒業した志願者から採用した予備学生に対して、在学中に徴兵猶予停止によって徴用された未卒業生から志願により採用した者を予備生徒という。 昭和18年10月2日、専門学校以上の学校の文科系学生に対する徴兵猶予が停止された結果。2,208名が1期予備生徒として加わった。 兵科、飛行科、整備科の3種に区分し、教育を修了したのは第1期、第2期のみで第3期は卒業に至らず終戦を迎えた。
|
|||||||||||||||||||||||||
|
学徒出陣 |
昭和18年12月太平洋戦争のさなか 旧制文科系大学・高専・専門学校学生生徒の多くは学業半ばにして召集を受け軍籍に身を投ず。これを学徒出陣と称す。 太平洋戦争の激化(戦線の拡大と相次ぐ敗北による兵力の極度の消耗)にともない、「国家存亡のとき、学生もペンを捨てて入隊せよ」とのスローガンの下、1943(昭和18)年12月、徴兵年齢(満20歳)に達した大学・高等専門学校の学生(理工科系・教員養成系以外)を入営させた措置。 最後の早慶戦で歌われた海ゆかば |
|||||||||||||||||||||||||
|
学徒壮行大会 |
昭和18年10月21日、
学徒壮行大会の実況 |
|||||||||||||||||||||||||
|
神風特別攻撃隊
「皆元気でゆこう。 |
海軍兵学校、予備学生、特務士官を含む神風特別攻撃隊での士官戦死者587名。うち飛行予備学生・生徒の戦死者が512名。87%が予備学生出身者で占められていた。 神風特攻隊、ナレーション 草薙隊、大塚晟夫(あきお)さん(23歳、中央大) |
|||||||||||||||||||||||||
|
予科錬 |
海軍飛行予科練習生の略称。旧日本海軍て、戦場における航空機の重視に伴い、多数の搭乗員を育成するため、1930年(昭和5年)霞ヶ浦飛行場内に設けられた制度。14~15歳の少年に約3ヵ年の基礎教育を施した。予科終了後、飛行練習生教程を経て搭乗員となった。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
三重海軍航空隊 三重県一志郡香良洲町 |
この門は三重海軍航空隊の門なり 過ぐる日紅顔の少年達がこの門をくぐり情熱のすべてを祖国に捧げ朝な夕なに訓練に励み大空へと巣立って行ったのは海軍飛行予科練習生である 祖国の安泰と民族の平和を念じつつ悠久の大義に殉じていったその霊を顕彰するためにもこの門を永久に保存するものである
|
|||||||||||||||||||||||||
|
海軍第一期飛行専修予備生徒慰霊碑 大阪護国神社
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
終戦 |
昭和20年8月15日 大東亜戦争終戦 | |||||||||||||||||||||||||